絵本の読み聞かせを習慣化できればこのようなことが期待できます。
- 長い絵本を聞けるようになる
- 人のお話を聞けるようになる
- 語彙が増える
読み聞かせに限らず、勉強やダイエットも習慣化させることって難しいですよね。「気合を入れて頑張るぞ!」とスタートしても熱があるうちは続くのですが、気づいたら3日坊主になっていた。というのはよくある話です。
「気合いを入れて短期間で習慣化させる」というよりも、「ゆっくり長く取り組むイメージ」で読み聞かせをする習慣をつくります。できる限り力を抜いてストレスなく読み聞かせができるように準備をしましょう。
絵本を読む時間帯を決める

絵本をいつ読めばいいの?
大前提として絵本の読み聞かせをいつするかは自由です。ここでは「読み聞かせの習慣化を目的」にした場合のお話をします。
習慣化が目的の場合「その時の思いつきで絵本を読むこと」よりも
決まった時間に絵本を読む重要性
「決まった時間が来たら絵本を読む」
この仕組みを作ってしまえばムラなく毎日絵本を読むことができます。例えば「就寝前に絵本を読む」と決まっていれば、忙しくても必ず絵本を読む時間が生まれます。
読み聞かせの時間が決まっていると
今から絵本の時間だね!
と、子どもの気持ちスイッチが入りやすくなります。食事や歯磨きと同じで「読み聞かせをしないと気持ち悪い」という状態になることが理想です。
就寝前の読み聞かせ
習慣化しやすい読み聞かせのタイミングは「寝る前の時間」です。就寝前の時間は朝などの忙しい時間に比べて心に余裕を持ちやすいです。ゆったりした気持ちで読み聞かせを行いましょう。
絵本の置き場所を工夫する
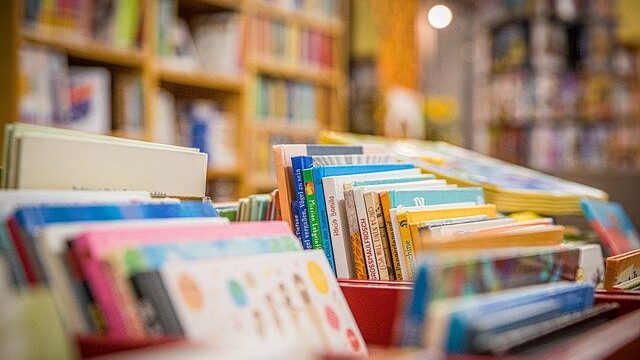
絵本の読み聞かせを習慣化させるには、子どもが絵本にたくさん触れて絵本を好きになってもらうことが大切です。そのために「子どもが自分から絵本に手を伸ばしたくなる工夫」をしましょう。
寝室とリビングに絵本棚を置く
お家のどこに絵本棚を置けばいいの?
寝かしつけ前に読み聞かせをしたいのでまずは寝室に絵本棚を設置しましょう。
それとは別にリビングにも絵本棚を設置します。
読み聞かせを習慣化するには絵本に触れる機会を増やすことが重要です。家の様々なところに絵本があると絵本に触れる機会が増えます。
とはいえ、家中あちこちに絵本を置くのは片付けや管理の手間が増えます。そこで寝室とリビングの2部屋に絵本棚を設置することがバランスが良くてオススメです。
リビングと書きましたが、正確には「子どもが昼間活動している場所」です。リビングや子ども部屋の家庭が多いのではないでしょうか?ご家庭によって環境が違うので説明しやすいように「リビング」と統一して解説します。
子どもの目に絵本が触れる機会を増やす
リビングに絵本棚を設置する最大のメリットは「子どもが絵本に触れる機会が増える」ことです。
- おもちゃ
- テレビ
- リモコン
- スマホ
子どもは目に入ったものに興味を持ちます。絵本が目に入れば絵本に興味を持つ可能性があります。しかし、身近に絵本がなければ興味を持つチャンスを失ってしまいます。
リビングの絵本は子どもが
これ読んでー!
と持ってきたときに読みます。
ポイントは「子どもが自分から絵本を持ってくる」ところです。
読み聞かせを習慣化させるには絵本を好きになってもらうことが大切です。興味を持たなければ好きになることはありません。
「読み聞かせをする時間」は就寝前にすでに確保してあります。
リビングでの読み聞かせは「子どもが自分から絵本に興味を持つ」ことを狙っています。
時間帯によって絵本を使い分けやすい
もちろん、絵本はどのタイミングでどんな絵本を読んでも良いのですが就寝前に
- 興奮する絵本
- 怖い絵本
- 頭を使う絵本
就寝前の読み聞かせには向いていなくても、素晴らしい絵本はたくさんあります。そこで、部屋によって読む絵本を変えることをオススメします。
- ゆったりした絵本
- 心の落ち着く物語の絵本
- ドキドキ興奮する絵本
- 図鑑や化学の絵本
さらに、子どもが自分から絵本に興味を持つことを期待して
- 新しい絵本や珍しい絵本
- 子どもの興味がある分野の絵本
こんな感じで絵本を用意しています。しかし、寝室で新しい絵本を読んだりリビングでゆったりした絵本を読むこともよくあります。「この絵本はここ!」とはっきり決めているわけではありません。
ストレスを感じない程度に、良い意味で「テキトーな管理」が大切です。読み聞かせの習慣化は長期戦なので変に力を入れないでゆるく長く付き合うことがポイントです。
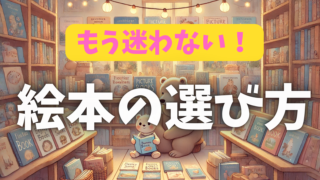
親が本を読む姿を見せる
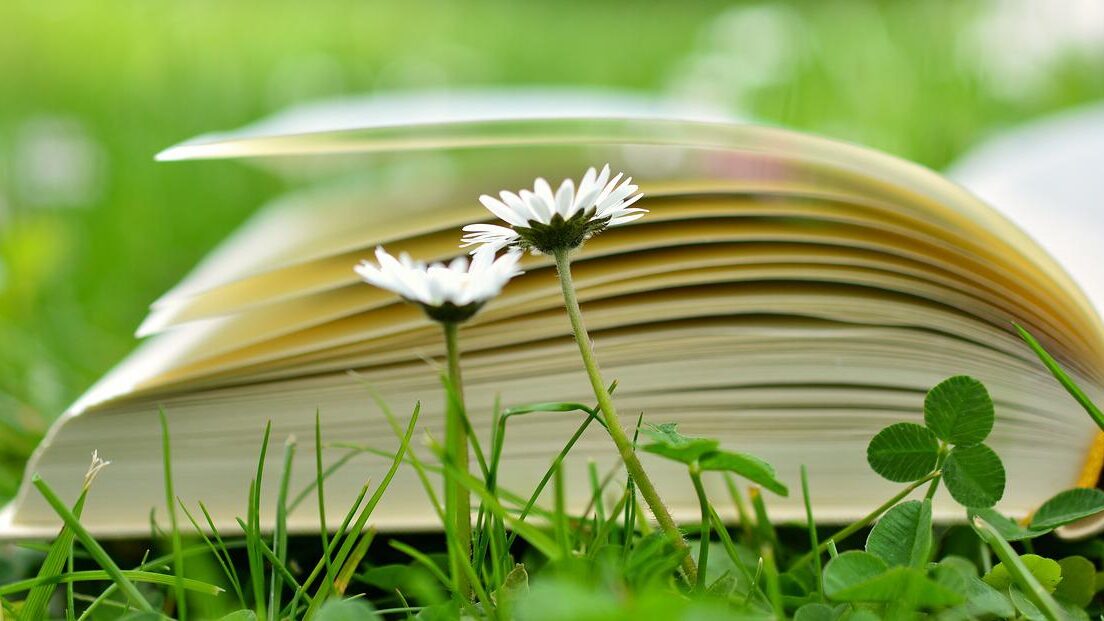
大人が楽しそうにしていることに子どもは興味を持ちます。「親の背を見て子は育つ」なんて言いますが、親が夢中になって読書をしていたら子どもはこう思うはずです。
本ってそんなに面白いの?
一緒に見たい!
どんな本を読んでもOKです。
- 小説
- 雑誌
- 絵本
- マンガ
- などなど
ただし、Kindleなどの電子書籍ではなく紙の本がオススメです。電子書籍も立派な本ですが、子どもから見るとスマホやタブレットをいじっているように見えてしまいます。
子どもが本に興味を持ってもらうことが目的なので、スマホやタブレットではなく紙の本を読みましょう。

はじめは短い絵本から読み聞かせ
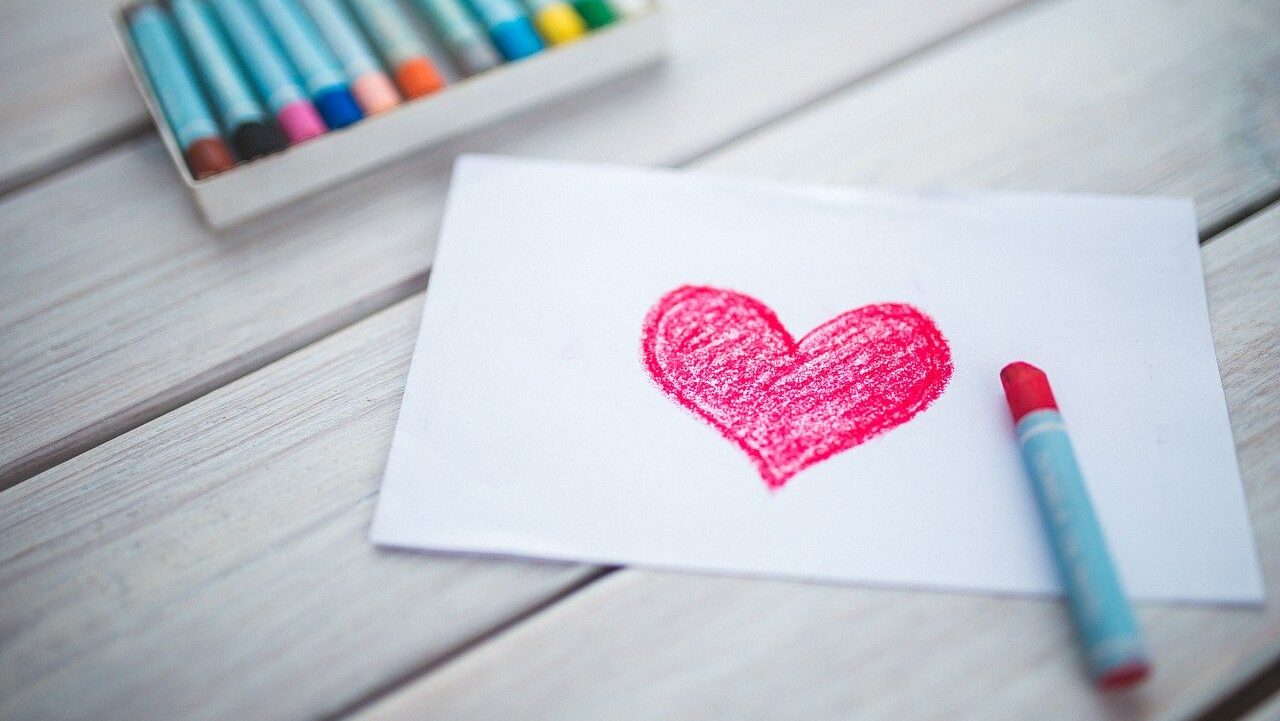
どんな絵本を読めばいいの?
読み聞かせを習慣化させる効果的な方法の一つは「絵本を好きになってもらうこと」です。子どもも大人も好きなことは続きやすいですよね。
いきなり長い絵本を読んで
絵本ってむずかしい!
好きじゃないかもー!
と子どもに思われてしまうと習慣化がしづらくなってしまいます。
がんばって短い絵本を1冊読み切りましょう。もちろん、いきなり全部聞いてくれるとは限らないので焦らずに!
お子さんが短い絵本を1冊最後まで聞くことができたら
と声をかけましょう。こう言われたお子さんは
自分は絵本を最後まで聞くことができるんだ!
という自信がつきます。
自信がつくと「次も頑張って絵本を聞いてみよう」という気持ちになります。
短い絵本が読めたら
- 他の短い絵本
- 文字の少し多い絵本
- ちょっと長い絵本・・・
と時間をかけてステップアップしていきます。
「この絵本も聞けたねー」と1冊ずつ声をかけることで「自分は成長しているんだ!もっと長い絵本も聞けるぞ」と、どんどん自信がついていきます。
繰り返し絵本に触れているうちに絵本を好きになるというわけです。

挫折しそうになったら

子どもが絵本を聞いてくれなくて心が折れそうだよ
こういう時は読み聞かせを数ページでやめても大丈夫です。数ページ読むのもキツければ「とりあえず絵本を開く」そこまででもOKです。
子どものために絵本を選ぶのももちろん良いですが、
「今日は、私がこの絵本を読みたいな」という親主観で絵本を選んでも良いと思います。
絵本を読むのが義務になるとツラいし続きません。絵本を読む親自身も絵本を楽しむようにしましょう。
よたろう
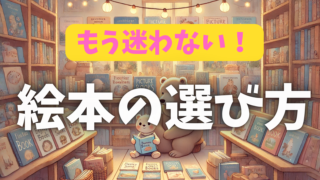
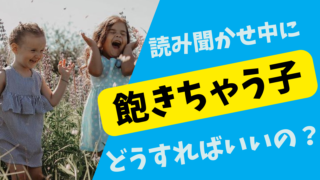












…と、考えすぎないでください!!